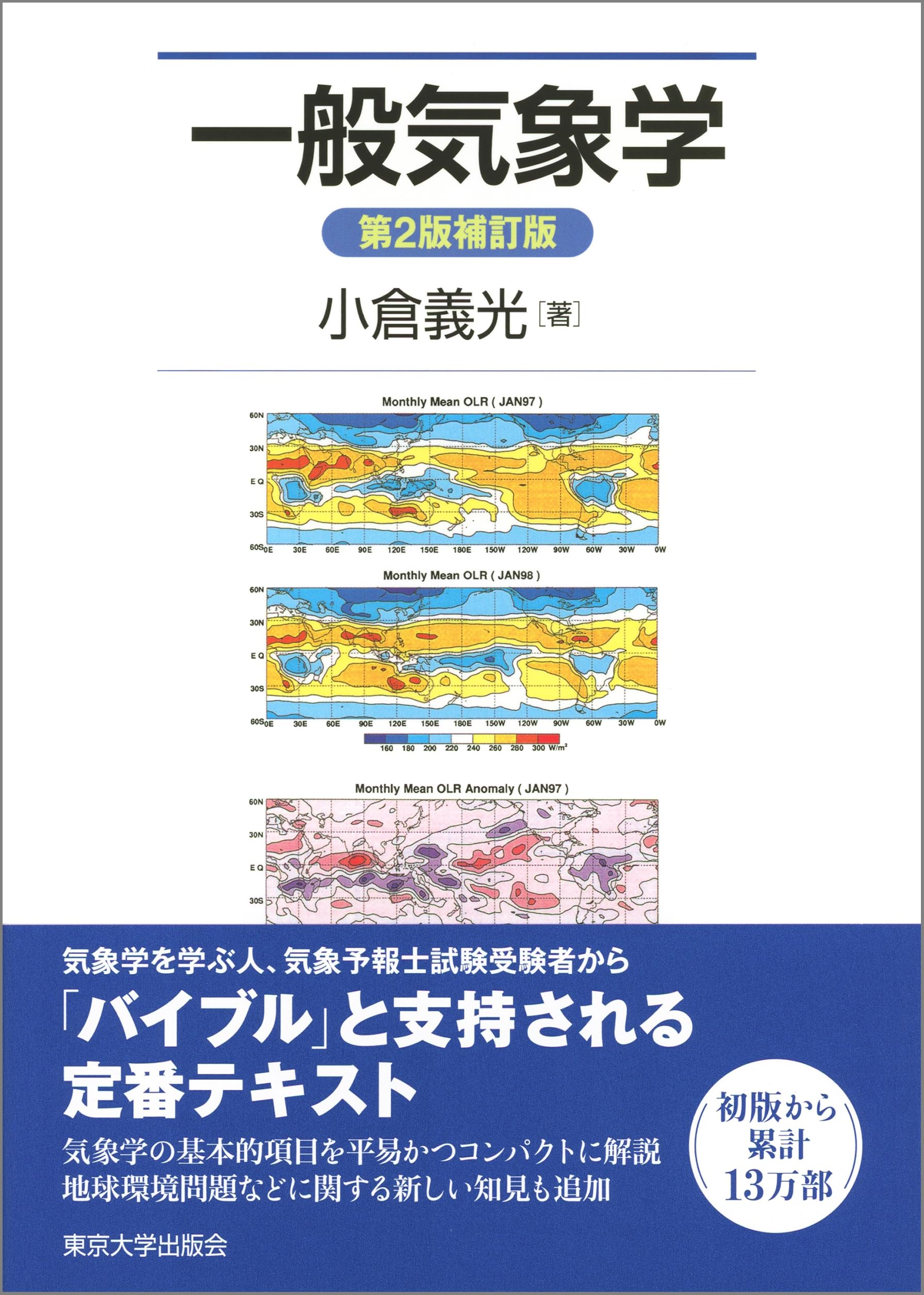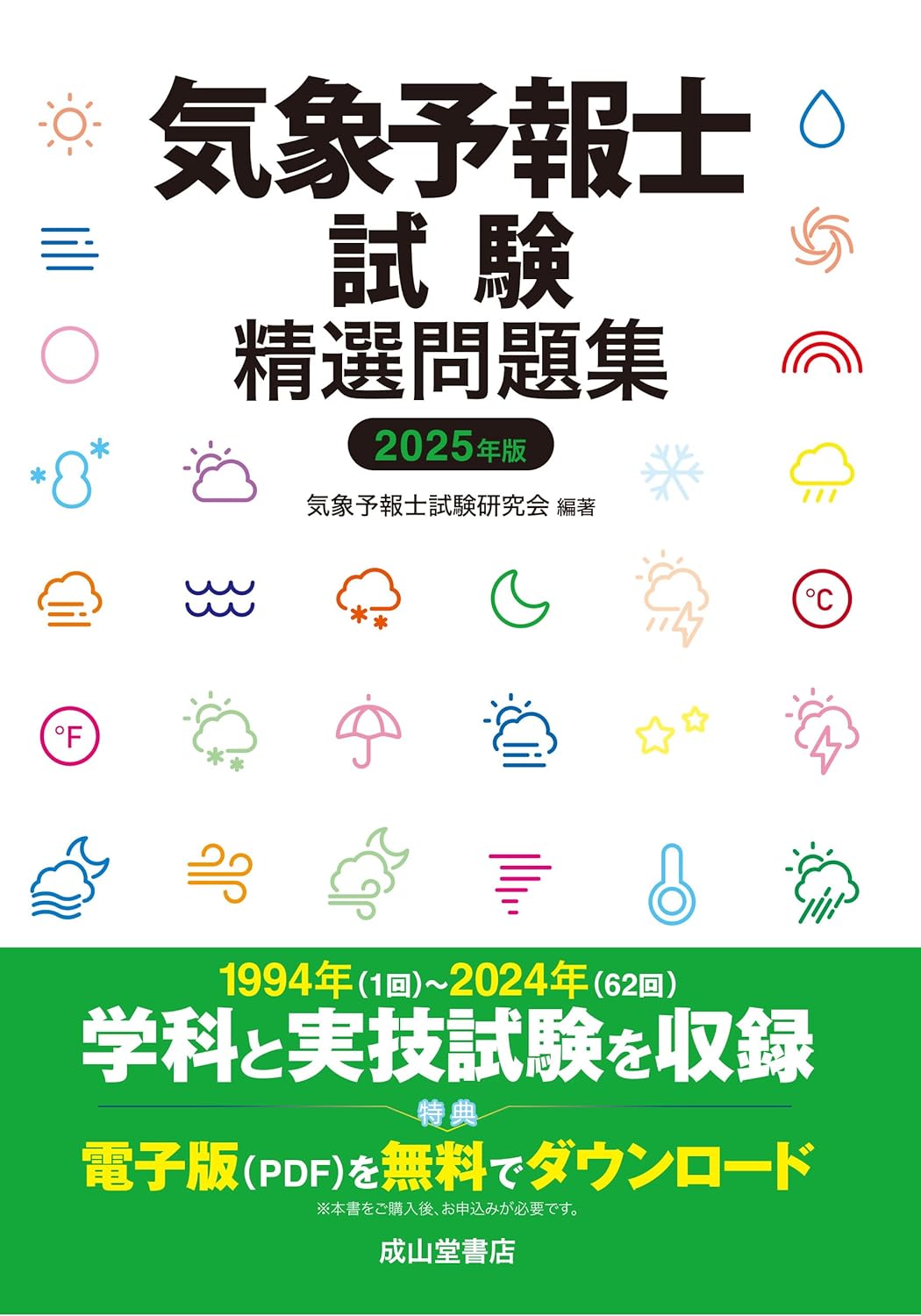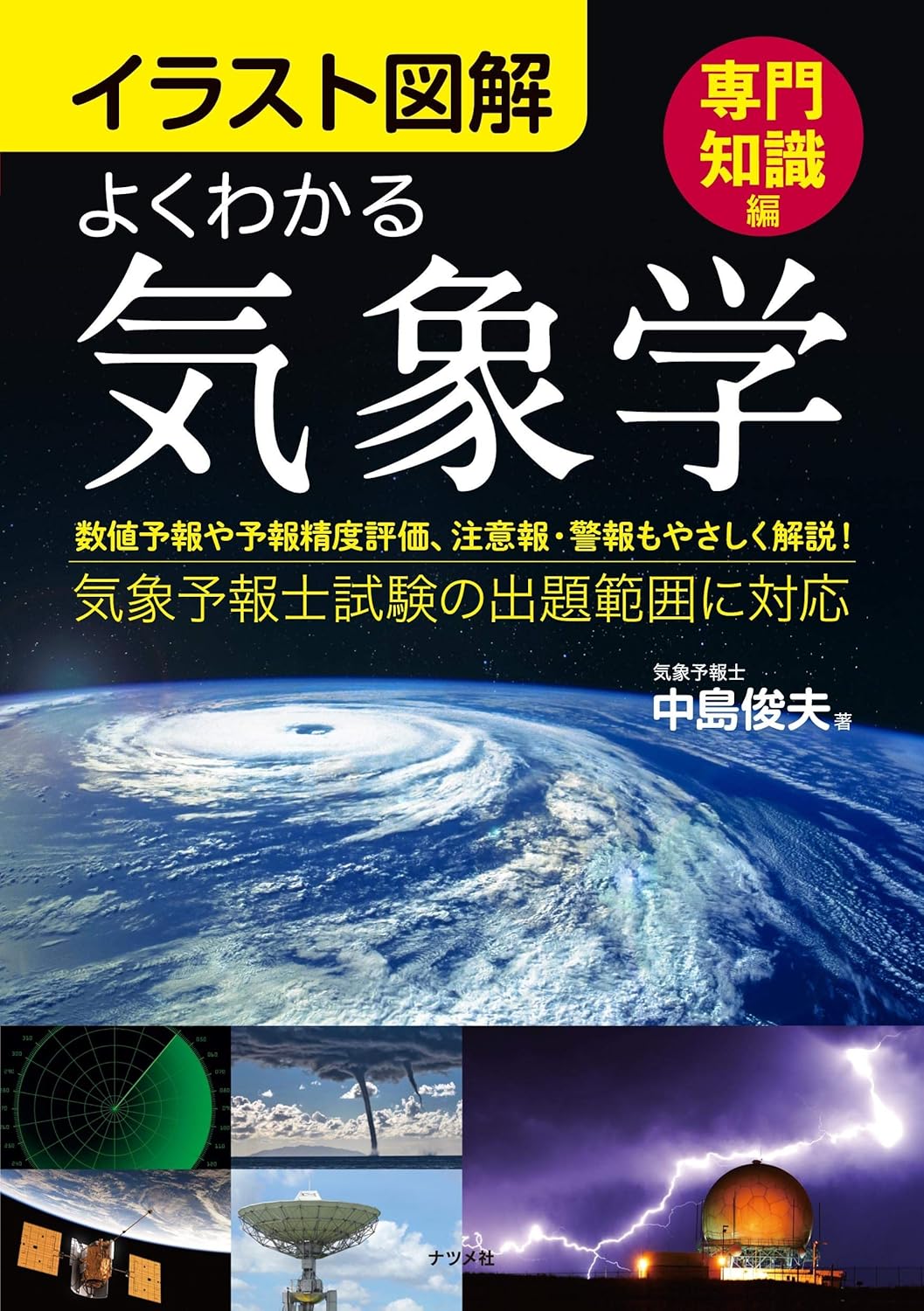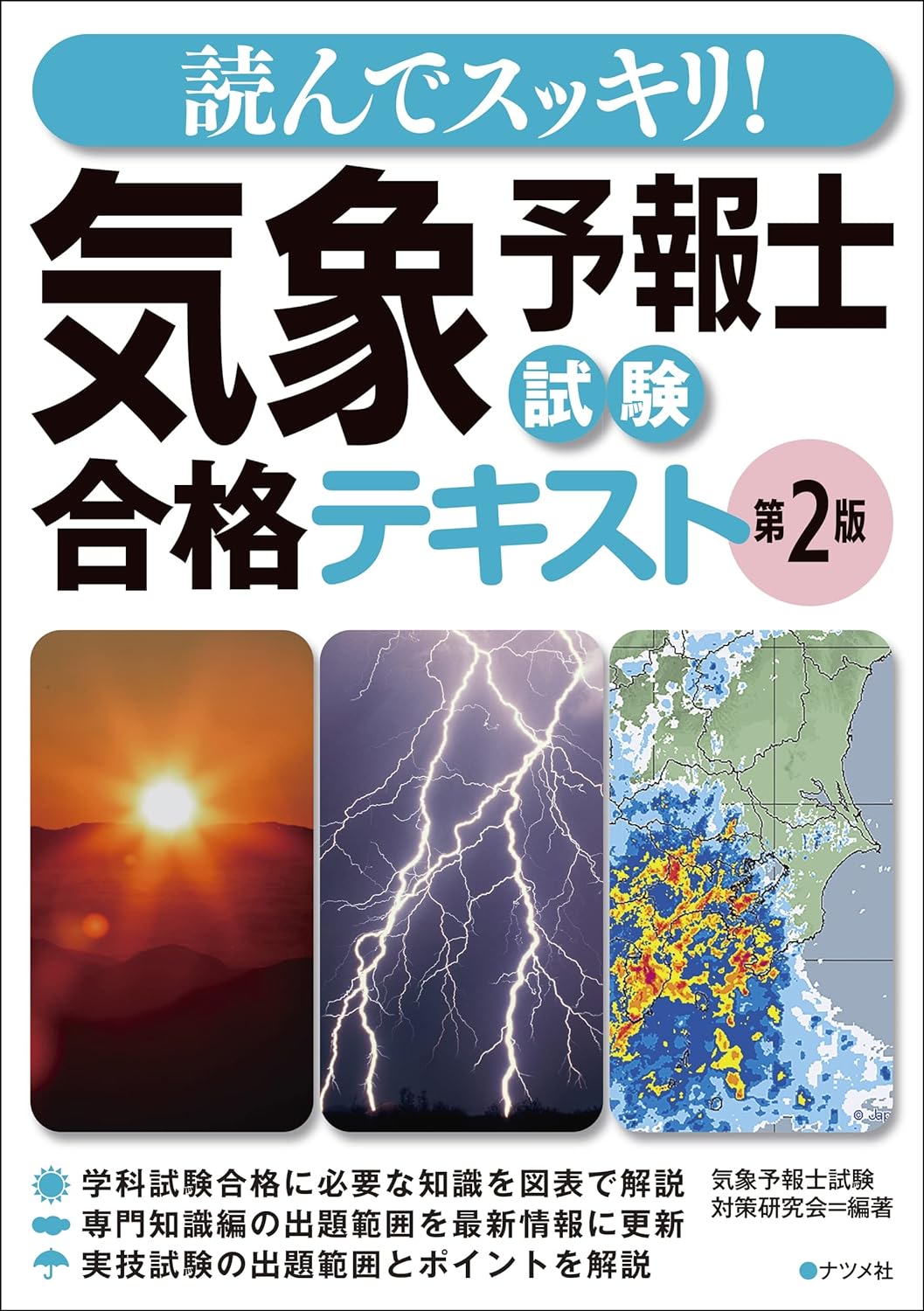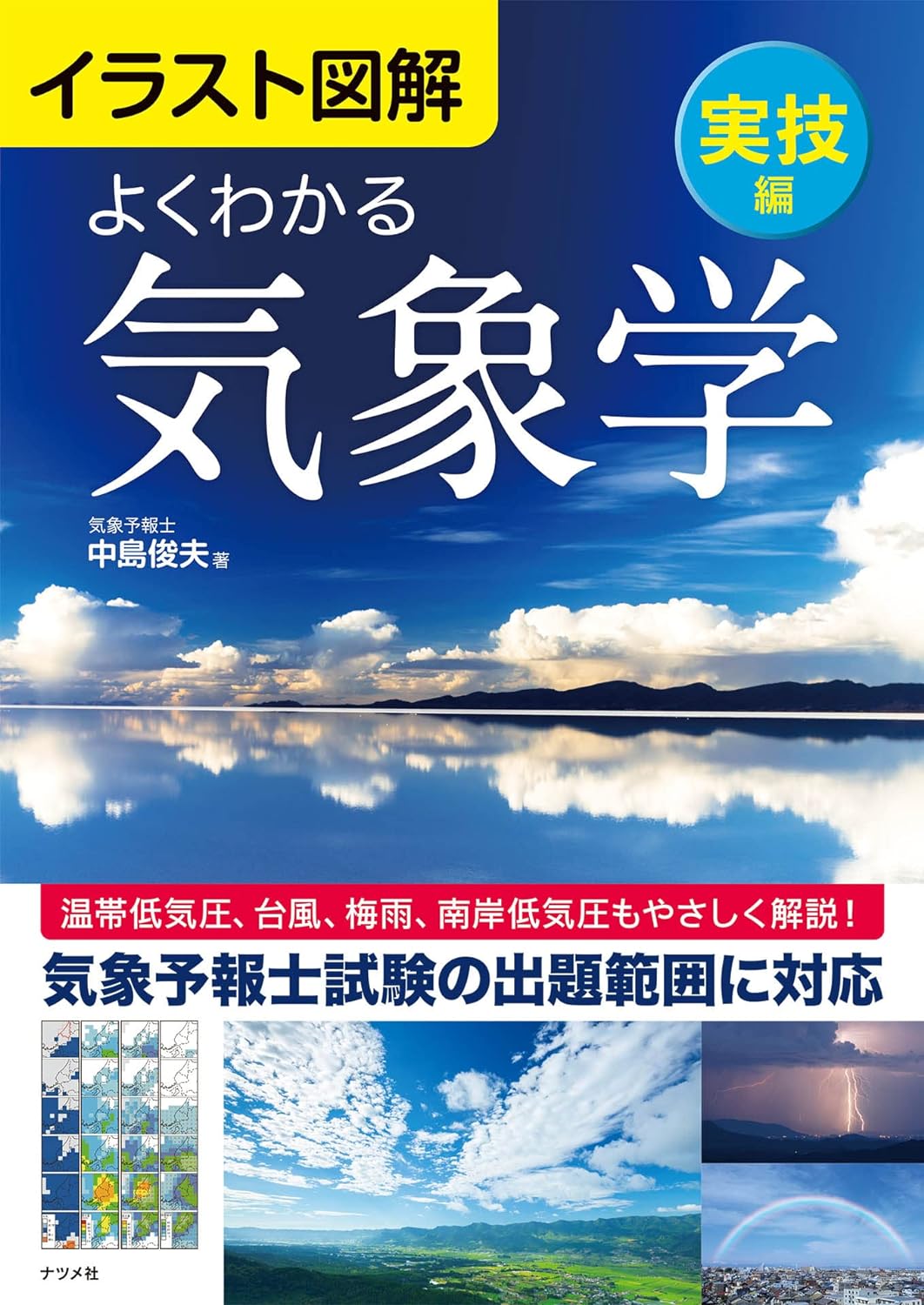気象予報士試験
合格までの流れと、勉強法
独学で、第63回気象予報士試験に一発合格しました。
我ながら、かなり効率的に勉強を進められたと思うので、これから目指される方のために記録を残します。
勉強法について手早く知りたい方は、1は飛ばして、2からお読みください。
1 合格までの流れ
勉強を始めたのは試験の6ヶ月前(2024年8月半ば)です。社会人なので、普通に仕事をしながらの勉強です。
1〜2ヶ月目:学科一般
最初は、何から勉強を始めればよいのか分からず、手探りの状態でした。そこでまず、定評のある『一般気象学』(下記)を読むことにしました。
約2ヶ月間、とにかく「内容を理解すること」を最優先に、何度も繰り返し読みました。結果として、3〜4周ほど読み込むことになりました。
3周目を終えた頃には、「割と定着してきたかな」と感じるようになり、問題集を解き始めました。使ったのは、『気象予報士試験 精選問題集』(下記)の一般(法律除く)です。全部解いたところ、すでに正答率が約70%に達していました。
その後、問題を総復習(3周)し、一般分野の学習をひとまず完了しました。
一般気象学(小倉義光)
白黒で古そうな見た目ですが、読み始めてみると(読み物としても)とても面白い本です。個人的には「面白いので何度も読んでいると、自然と点が取れる」というおトクな本です。ただし時代の流れを考えると、この本にこだわる必要はないのかもしれません。
※ ここで紹介している本は、すべてオススメです。
気象予報士試験 精選問題集(気象予報士試験研究会)
この本はメチャクチャやり込みました。この本を完璧にして、過去問を3年程度解いたら、演習量としては合格ラインなのではないでしょうか。
なお,「実技の解説が文字ばかりで分かりづらい」という批判があるようですが,個人的にはむしろ「文字の解説」が記述の勉強になって良かったです。
3〜4ヶ月目:学科専門
まずは中島さんの『よくわかる気象学【専門知識編】』(下記)を読みました。
読んでみて感じたのは、「これは暗記ゲーだな」ということです。そこで、文房具店で緑マーカー・赤ファイルを購入しました。これを買うのは、大学受験以来のことです。
しかし、読み進めるうちに、この本は復習には向かないと感じました。繰り返しの記述や冗長な表現が多く、読むだけでも余計に疲れるためです(どちらかというと「講義調」の本です)。
そこで選んだのが、 『読んでスッキリ!』本(詳細は下記)です。この本は解説はコンパクトですが、逆に言えば「試験に出る部分だけ」が詰まって書かれています。復習には最適な本です。
早速、緑のマーカーを引いて読み進め、3週間ほどで内容をすべて暗記しました(余談ですが、「法律」も全く同じ要領で勉強しました)。
その後、先ほどと同様に『気象予報士試験 精選問題集』の専門をすべて解いてみたところ、正答率はすでに約70%に達していました。
読んでスッキリ! 気象予報士試験 合格テキスト 第2版
この本1冊を完璧にすれば合格できます。それくらい網羅性の高い本です。しかし、解説がコンパクトすぎるので、最初は上の『よくわかる』から入ったほうが良いかも。
また、法律の章がきちんとあるのも大変ポイントが高いです。
5〜6ヶ月目:実技対策
まずは、中島さんの『よくわかる気象学【実技編】』(下記)を読み、巻末の問題を解きました。
実際に解き始めて気づいたのは、時間がまったく足りないということです。ただし、時間をかけさえすれば、一般・専門の知識だけで合格点(70%)近く取れることも分かりました。
これは「慣れゲー」だな、と思いました。ひたすら問題を解いて、解答時間を短縮していく。そして、記述問題ではテンプレート的な回答を「習得」することも必要です。
しかし、ここでひとつ落とし穴がありました。『中島本』の問題は比較的古く、難易度も易しめだったのです。最近の問題のほうがむしろ難しいと気づいたときには、すでに試験まで1ヶ月を切っていました。
そこであわてて、『精選問題集』(上記)の実技問題を解きまくり、さらに過去問も3年分ほど解いて試験に挑んだ、という流れです。
試験結果
学科はどちらも13点でした(最低点は共に10/15)。実技試験の自己採点は72%で、最低点が60%だったのには少し驚きました。
結果として、ある程度の余裕を持って合格できたのではないかと思います。それでも、発表直前はやはり緊張しましたが。
2 合格の秘訣
いちばん大事なこと
いちばん大事なことをまず初めに述べます。
一般は「理解ゲー」です。
専門は「暗記ゲー」です。
実技は「学科の理解」+「慣れゲー」です。
順を追って説明します。
「一般」の勉強法
教科書は何でも良いと思いますが、とにかく「理解」に努めることが大事です。
一般知識は、サイエンスとしての「気象」の理解度を図るものです。丸暗記では対応できません。というか、丸暗記で対応しようと思うのが、そもそも「サイエンスの専門家」を目指す態度として間違っています。
例えば、あなたは次の問に答えることはできますか。
相当温位とは何か。
この問いにスラスラ答えられないということは、そもそもあなたはまだ何も理解していないと考えるべきです。用語の意味もよく分からないのに、問題が解ける訳ありません。
「専門」の勉強法
これは言わずもがな、理解したらひたすら「暗記」です。
(もちろん、「理解するな」と言っているわけではありません。理解は絶対に大事ですが、一般知識に比べればハードルが低い、ということです。)
暗記に欠かせないのが「反復」です。あなたはこんな経験はありませんか?
教科書は読んだけど(問題は解いたけど)、1ヶ月経ったら全部忘れちゃった。
これは単に反復が足りていないだけです。——逆に言えば、1日で完璧に覚える必要はありません。暗記できなくても、次の日に復習し、またその次の日に復習する——それを繰り返せば自然と記憶に定着します。
私が個人的に目安としているのは「3周」です。問題集なら、最低でも3回は解くようにします。
一冊を繰り返し解いて完璧に仕上げるのが、最も効率的な勉強法です。受験勉強を真面目にやったことがある人なら常識ですが、できない人に限って、いろんな参考書に手を広げてしまいます。それは厳禁です。
「実技」の勉強法
これは結局のところ、「慣れ」だと思います。目安として、15〜25事例以上を解いて合格する人が多いようです。
ただ、実技試験特有の課題として、「記述対策」があります。これに関しては、問題を解きながら語彙を増やしていくしかないと思います。
例えば、「衛星画像の雲域の形状・分布について述べよ」と聞かれたとき、最初はどのように答えればよいのか、分からないものです。答えとして,あなたはどのような語彙を持っていますか?
すじ状の雲域/帯状の雲域/渦状の雲域/塊状の雲域/のびている/まとまっている/広く分布している/⋯
たくさんありますね⋯。解答を見て知らない表現に出会ったら、その都度調べて「自分の言葉」として身につけていきましょう。これを20事例ほど繰り返せば、合格点に到達できるはずです。
また、『中島本』に書かれている重要事項は、スラスラ言えるようにしておきましょう。例えば、以下のようなものです。
温帯低気圧の発達条件を3つ述べよ。
前線解析も同様に、しっかりと覚えておくべきポイントです。試験本番でテンパってしまったとしても、『中島本』の手順通りに前線を引いておけば、大きな減点を受けることはないはずです。
法律(気象業務法など)
さいごに、法律について軽く述べます。
法律というと「理系は苦手で、文型が有利」という解説をよく見ますが、その方は法律の読み方を何も分かっていないと思います。
気象業務法を最初から読んでみてください。最初に登場するのは「用語の定義」です。その後、観測についていくつかの「場合分け」をし、義務が定められています。
まずは用語を定義し、その後場合分けをし、それぞれの条件ごとにストーリーを進めていく——これ、実は数学の議論の進め方と全く同じなのです。
もちろん結局は暗記しますが、「ストーリー」をきちんと意識することで、暗記がグッと楽になるはずです。
補足 令和5年度に気象業務法が改正され、民間企業への「洪水」予報業務許可が可能になりました。いずれ試験に出る気がするので、そこもチェックしておきましょう。国交省のサイトで改正の差分がチェックできます。
3 補足
過去問に入るときの目安
私の経験では、教科書をある程度理解していれば、初めてでも5〜7割はすでに解けるはずです。それすら達しないのであれば、教科書の理解や暗記が不十分なのだと思います。
過去問は10年分が目安
なお、他のサイトで「過去問は可能な限り多く解け」と書かれていることがありますが、個人的にはあまり賛同できません。もちろん過去問は大切ですが、20〜30年以上も解く必要があるのでしょうか。それで本当に楽しいですか? 気象が嫌いになってしまいませんか?
正しく勉強していれば、無理する必要はありません。自然な努力の範囲で合格点を目指しましょう。
なお,前述した『精選問題集』がだいたい過去問7年分(実技は5年分)なので,学科は残り3年分だけ解けばいいわけです。うまく行っていれば,この時点で既に12〜13点くらい安定して取れているはずです。
「一問一答集」は使わない
受験勉強を真面目にやったことがある方なら、「『一問一答集』を使っている学生は、決まって模試の成績が悪い」というのは常識だと思います。
なぜそうなるのでしょうか⋯。私の考えでは、理解せずに暗記に走ってしまうからではないかと思います。とにかく、使わないようにしましょう。別に一問一答集を使わなくても、学科試験は13〜14点取れるので、安心してください。
強いて言うなら、こういった教材は「実技も含めて十分に勉強し終え、時間が余っている人」向けでしょう(そんな人、いないと思いますが)。
実技試験当日の注意
やって良かったと思ったのは、受験票をテープで机に固定しておくのと、ペーパークリップで切り取った図表をとめたことです。
ここは人それぞれだと思いますが、色鉛筆は要らないと思います。勉強中に「色鉛筆あればよかった」と思ったことは一度もなかったので、私は試験当日も持って行きませんでした。ちなみに、コンパスはたま〜に使うことがあるので、持っていった方が無難です。
また、本番のテクニックとして、30秒以上考えてもわからない問題があれば、適当に書いて次へ進みましょう。実技試験で目指すべきは、満点ではなく80点です。
4 それでもうまくいかないとき
それでも「実技」がうまくいかないとき
学科の勉強からやり直すことをおすすめします。
いくら実技試験の訓練を積んでも、そもそも基礎知識が足りてないので、成績が伸びていない可能性があるからです。
あなたは学科試験で何点を取って合格しましたか?「たまたま11点取れて免除になった」というのであれば、まだ基礎が固まっていません。正直なところ、学科試験は13〜14点を取れてなんぼの試験です。
確かに、学科試験では毎年1問、(凡人の満点を阻止する)難問が出題されることがあります。しかし、それ以外の問題は確実に正解するべき内容です。仮に1問ミスしても、13〜14点は取れるはずです。
また、もし独学で難しいと感じるのであれば、無理にこだわらず、講師をつけて指導を受けるのも選択肢でしょう。個人的には、中島さんの教え方やアドバイスが非常に分かりやすく好きなので、そこに行くのが良いかもしれません。
「一般の計算問題」でつまづいているとき
一度、高校物理を勉強してみることをおすすめします。
「一般の計算問題は難しい」とよく言われますが、実は理系出身の人にとって計算問題は得点源です。
大学の勉強は関係ありません。高校の「物理」または「物理基礎」の教科書を取り出し、「力学」「熱力学」の章だけ読んでみてください。これから気象の専門家を目指すのですから、その基礎となる物理学を理解しておくことは無駄ではないはずです。
5 さいごに
今の時代、気象予報の主役は 「数値予報 × AI」です。そう考えると、気象予報士は予報の主役ではないのかもしれません。私たちの役割は予測ではなく、予測結果を目的に合わせてカスタマイズし、結果に責任を持ち、それを適切に解説することです(AIは責任を持つことができませんからね)。
先月、とあるイベントで、(最近新しく就任された)気象庁長官のお話をお聞きする機会がありました。そのときに聞いた言葉は、今も心に残っています。
ビジネスにとって気象とは、塩や砂糖のようなものである。
私達は塩しか提供しない。肉や魚を用意し、調理するのはあなた方の番だ。
気象予報士になったからといって、必要以上に誇るのは控えましょう。この「資格」を自慢にしている人——「塩」だけなめている人——が一番「ダサい」です。